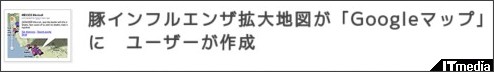Googleマップの良い使い方の一例
以前に、住所という「文字情報」から、色々できる「地図画像情報」に変わるイノベーションの功罪で書きましたが、Googleマップが意図しない状態で公開されたり、身内だけで見るために作られた地図に必要以上の個人情報まで記載されたページが、誰にでも見られるようになっていた・・・など。。。Googleマップの本来あるべき姿は、これだ!と思うのです。
豚インフルエンザ拡大地図が「Googleマップ」に ユーザーが作成 – ITmedia News via kwout
世界で感染が広がっている豚インフルエンザについて、感染の拡大状況を確認できる地図が、「Googleマップ」のプラットフォームを活用していくつか登場している。
それぞれ個人が作成したとみられ、メディアから情報を得るなどして拡大状況をプロットしているようだ。情報の信頼性が担保されているわけではないが、参考程度にはなるだろう。
世界中の人たちが、インターネットを通じて、感染状況を把握できるのがいいですね。
この地図と、ニュースなどの情報を自分なりに咀嚼して、状況をつかめれば良いと思います。地図だけの情報だと、その真偽は見極められませんし、ニュースだけの情報も「視聴者にすべてを伝えていない」ことを考えると、様々な情報を自分で認識する。ことが大切だと思うのです。
既に、インフルエンザに便乗したコンピュータウィルスや、悪意なツールが出回っています。デマ情報も流れてくることでしょう。
自分で見極める力をつけたいものです。
現状の情報セキュリティ教育研修をそのまま続けて大丈夫ですか?
ほとんどの企業において、情報セキュリティ教育のコンテンツは一巡しています。新たに知るべく脅威などもありますが、ほぼ新しいコンテンツはありません。
技術者の方々は、常に最新の動向を知る必要があります。しかし、一般社員の方々が知るべくことは技術者の方々とは内容が違います。
一般社員の方々に向けた「情報セキュリティ」に必要なことは、ほぼ伝えきられたと考えます。
現在行われているのは、二巡、三巡の繰り返しです。同じことを反復練習していても情報漏洩事故は減少していません。
技術者の方々は、常に最新の動向を知る必要があります。しかし、一般社員の方々が知るべくことは技術者の方々とは内容が違います。
一般社員の方々に向けた「情報セキュリティ」に必要なことは、ほぼ伝えきられたと考えます。
現在行われているのは、二巡、三巡の繰り返しです。同じことを反復練習していても情報漏洩事故は減少していません。